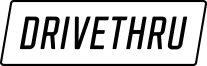Kiaという存在
海外へ行くたびに、不意に目を奪われる車がある。それはコリアンブランドの《Kia(キア)》である。降り立った空港。はたまた街中やあらゆる場所で。いつも〈Kia〉に目がいってしまう。それと同時に海外市場において、かつて日本車が築いた牙城を軽やかに塗り替えていることにも早い段階から気づかされていた。そんな〈Kia〉が遂に日本へ進出するという。幸運にも本国・韓国へのプレスツアーへの誘いを受け、多忙だったスケジュールを調整して参加することに決めた。これは単なる新ブランド上陸以上の意味を持ち、〈Kia〉には従来のカーメーカーとしての概念を超えた何かが宿っており、その謎を知る必要があったからだ。

2025年春の「Kia EV DAY」で発表された最新EVのラインナップ。(photo by Kia)
根幹にあるムーブメント
プレスツアーには日本のみならず、世界中から多くのメディア関係者が集まり熱気に包まれていた。プレスカンファレンスでは、ブランド戦略やニューモデルのプレゼンテーションが行われ、なかでも印象的だったのは、〈Kia〉のブランドスローガンとされる “Movement that inspires(インスピレーションを与える動き)”に基づき、電動モビリティを主軸に世界中でムーブメントを起こそうとしている姿勢だった。そもそも〈Kia〉は、80年以上もの歴史を持ち、創業当時は自転車の製造からはじまり、現在は乗用車をメインに、今や〈トヨタ〉〈フォルクスワーゲン〉に次ぐ世界第3位の規模にまで登り詰めたグローバルブランド。1999年に〈ヒョンデ自動車グループ〉の一員となり、2000年代には〈アウディ〉や〈フォルクスワーゲン〉のデザインを指揮した腕利きカーデザイナー、ピーター・シュライヤーを迎え入れ、デザイン経営に舵を切る。その後、グローバルな舞台で頭角を表し、近年では2021年にブランドロゴを刷新し「Kia Motors」から「Kia」へとミニマムな社名に変更。トップ3でありながら従来の自動車メーカーの枠にとらわれないモビリティカンパニーへとさらに進化しようとしている。
デザイン哲学に訳がある
〈Kia〉の革新的な姿勢を端的に世界に示したのは《Kia・EV6》という1台がある。独自のモビリティ像を表現し、EVのアーリーアダプター向けに2021年に市場投入されたモデルだが、すでに5年近く経っている現在も街角でみかけるたびに異彩を放っている。通常、最新モデルとなると時間が経つにつれて見劣りしがちだが、〈EV6〉に至っては存在感を失っていない。その謎は〈Kia〉のデザインフィロソフィーにあった。「Opposites United(オポジッツ・ユナイテッド)」という独自のデザイン思想は、相反するものをあえて融合させることで、これまでにない価値を生み出すという考え方。例えば、「水」と「油」を組み合わせることで、まったく予測できなかったものをつくり出そうという発想。それは実際にプロダクトにもはっきりと表れており、既存のカーデザインの文脈に収まりきらないボディスタイリングが、人の目を惹きつけ、新たな常識をグローバルな市場に提案している。

2023年に香港の街角で見かけた〈KIA・EV6〉。エッジの効いたデザインが際立っている。
日本導入はEVバンが最適解
面白いのは〈Kia〉が初めて日本市場へ投入するモデルが《PV5(ピービーファイブ)》というマルチパーパスなバンなこと。メインはコマーシャル向けだが、パッセンジャー向けも用意され、ボディはまるでレゴブロックのようにモジュール化されており、EV専用のプラットフォームを駆使したフレキシブルなカスタマイズができるという。ボクシーなバンタイプでありながら極めてスリークなボディスタイリングを纏い、〈Kia〉らしいデザインが随所に感じれる。さらに、床下にバッテリーを搭載しながらも低床なキャビンは実用面にも役立ち、バンとしての優れた性能を誇る。日本投入予定の〈PV5〉を実際にテストドライブすることができた。EVならではのシームレスな走りで、従来の商用バンとはかけ離れた低重心設計による上質なドライビングが印象的だった。あくまで加速感は決して恐怖を覚えるほどではなく、必要十分な力強さがある。ステアリングのパドルシフトでは回生ブレーキが調整でき、ワンペダルモードでも走行可能。さらにアクティブクルーズコントロールも装備し、安全性も充実。V2L(Vehicle to Load)機能による外部給電もでき、EVのバンとしての機能性と先進性を両立している。キャンパーへのカスタムも期待できる。
世界屈指のR&Dセンター
〈KIA〉の先進的なデザインを裏付けているのは最新テクノロジーにある。100万坪という規模を誇るヒョンデグループの「ナムヤン研究所」では、次世代モビリティの研究開発が行われ、今回の取材では、空力実験や耐久テストを行う施設を視察することができた。EVにおけるエアロダイナミクスの重要性は、電費性能や能航続距離に直結する。巨大なファンを備えた空力試験場では、日本導入を控える〈PV5〉がテストされていた。バンモデルのEVでありながらCd値が0.28を誇り、0.3未満であれば、優秀とされる世界で、商用バンがこの数値を叩き出すのは驚異的。エアロダイナミクスな技術によってフロントの形状やリアの処理までもが緻密に設計され、アンダーボディは限りなくフラットになっている。従来、空気抵抗が大きいとされてきた車種であっても、デザインと先進技術を掛け合わせることで別次元に導く。また熱エネルギー総合開発室という施設では、-40度の寒冷地を再現した実験や50度を超える高温時におけるバッテリーの耐久テストなどあらゆる地球環境に対応した耐久試験が行われていた。
日本市場は最難関
日本市場への参入は、世界でもっとも難しいとされている。大手国内メーカーがひしめき合い、ハイブリッドカーがガソリン車よりも普及した結果、マーケットはガラパゴス化が著しい。先進国でありながらEV普及率は未だ2%に過ぎず、一足先に再上陸を果たした〈ヒョンデ〉でさえ苦戦を強いられている。そんな中、〈Kia〉が満を持して日本市場へ投入するのは、あえてEVバンというのが興味深い。居住性が高く、仕事にも遊びにも活用できる電動マルチバンは、もはや車というより“モバイルリビング”であり、“モバイルオフィス”にもなり得る。自動運転や高度な運転支援が当たり前になりつつある今、〈Kia〉が提案するモビリティは、単なる移動手段を超えた暮らし方や働き方そのものを変えうる存在になるだろう。そう考えると、〈Kia〉が日本に持ち込もうとしているのは「車」ではなく、まさに彼らが掲げる「ムーブメント」そのものに違いない。
かつて日本車が、低価格でありながらユニークな発想と確かな信頼性を併せ持っていた魅力を、〈Kia〉がいま、世界の舞台で体現している。いつしか日本車は、ハイブリッド全盛期を境に本来の魅力を失いつつあるように思えてならない。一方、〈Kia〉は大衆車ブランドでありながら、手の届く価格の中に高品質と先進技術を融合させ、果敢に挑戦している。〈Kia〉の日本上陸が多くの人にリアルなモビリティ像を変えるきっかけになることを心から期待している。